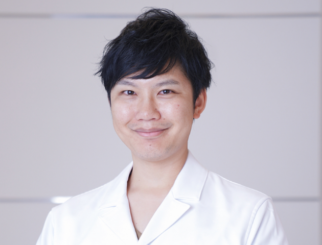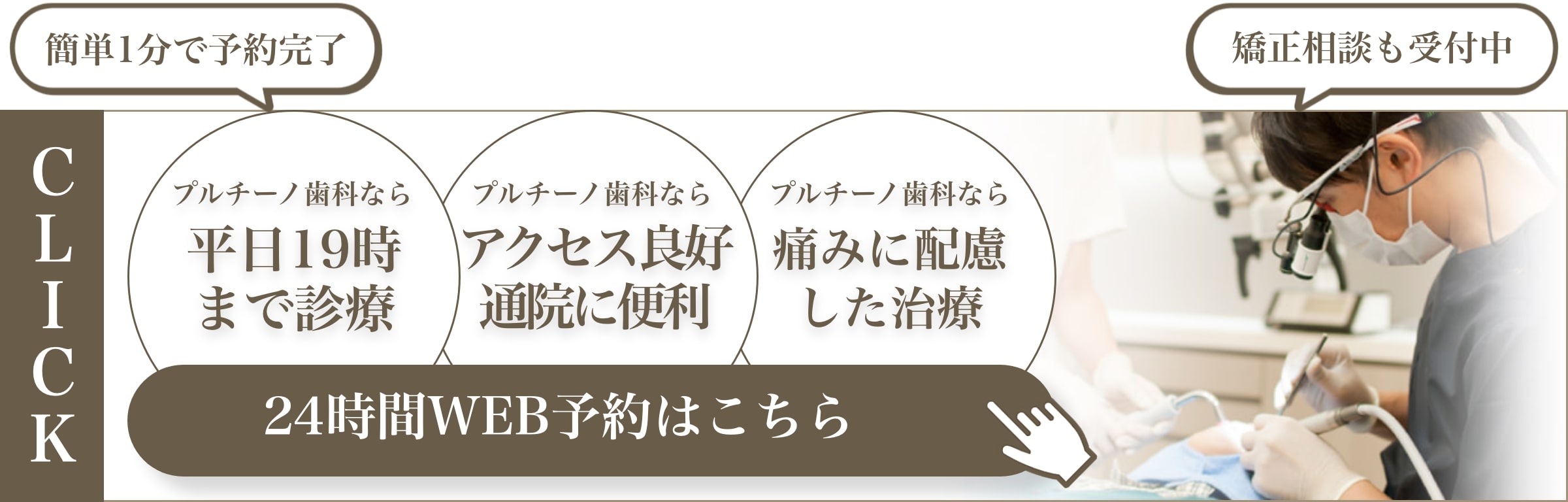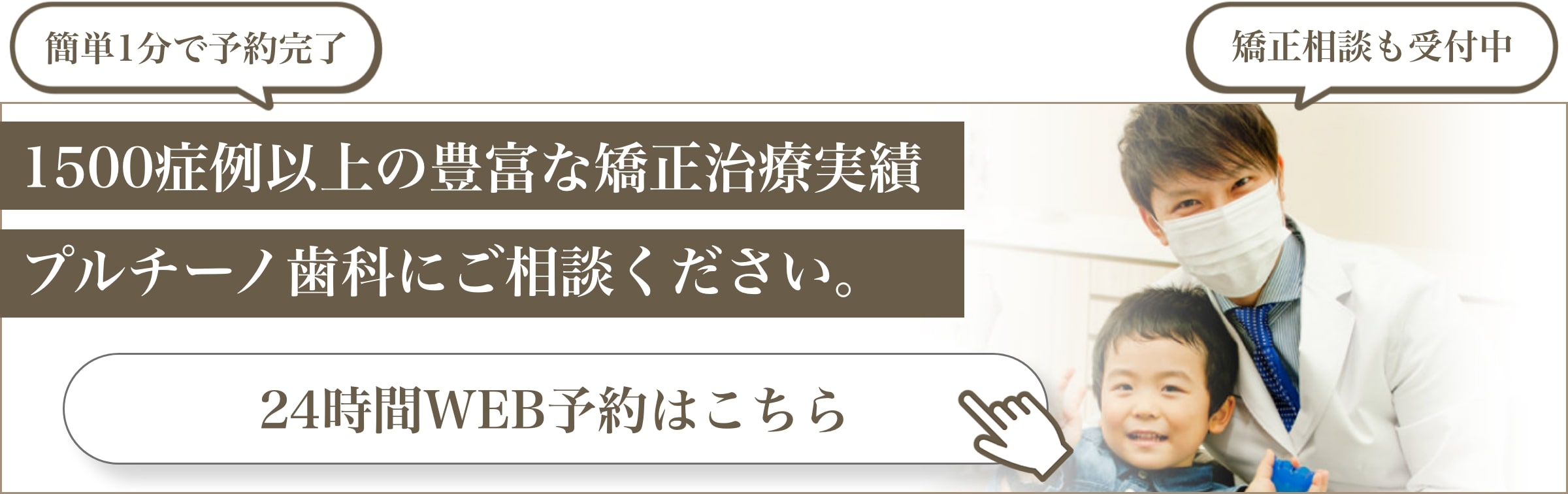歯列矯正の治療期間は、数年に及ぶのが一般的なので、これから妊娠予定の方や今現在、歯列矯正中で妊娠した方などは、どうしたら良いか迷われていることでしょう。妊娠中は身体が大きく変化するとともに、さまざまな制約がかかるため、そもそも歯列矯正は行えないのでは?と不安に感じているかもしれません。今回はそんな妊娠中の矯正歯科治療における注意点や避けるべき処置などをプルチーノ歯科・矯正歯科 四日市院がわかりやすく解説をします。
目次
【1】妊娠中や授乳中でも歯列矯正は可能です
結論からいうと、妊娠中あるいは授乳中であっても歯列矯正は行えます。そもそも歯列矯正は、専用の装置で矯正力を働かせて、歯をゆっくりと動かす治療なので、妊娠や授乳に大きな影響が及びにくいのです。もちろん、歯列矯正の診療プロセスには、侵襲性の高い処置も一部、含まれますが、それは適切なタイミングを見計らって実施すれば良いことでしょう。具体的には、後段で解説します。
① 体調に合わせて治療計画の見直し
妊婦さんは日々、体調が大きく変化します。妊娠期全体を通しても、安定している時期とそうでない時期とがあるので、歯列矯正の治療計画もその点を踏まえた上で立案、あるいは見直しすることが大切です。これは歯科医師と相談しながら決めていくことでもあるため、妊婦さんの歯列矯正を行った経験が豊富な先生の方が望ましいです。また、妊娠中に体調が悪くなった時は、遠慮せずに主治医に相談しましょう。身体や矯正に関する問題を自分だけで抱え込んでしまうのは良くありません。
② 悪阻(つわり)対策
妊娠中は、つわりの症状に悩まされる時期があります。これは妊娠期における生理現象なのである程度は許容せざるを得ません。ですから、つわりによる影響は、歯列矯正サイドで調整や、対策を講じる必要があります。
まず、歯磨きに関しては、つわりがひどい時に無理して実施する必要はありません。つわりの症状が現れている時はいったん歯磨きをお休みして、うがいだけで対策しましょう。その際、低刺激のマウスウォッシュを使うと、口腔内細菌の繁殖を抑えやすくなります。つわりの症状がそれほど強くない場合は、ヘッドの小さい歯ブラシでゆっくりと丁寧に磨くと良いでしょう。子供用の歯ブラシなら、口腔粘膜を刺激することも少ないのでおすすめです。
矯正装置による刺激で、つわりの症状が強くなっている場合は、主治医に相談して調整などを加えてもらいましょう。生活に深刻な悪影響が及んでいるケースでは、一時的に矯正装置を外すこともあります。そこでは主治医と相談しながら決めていきます。
③ 体調第一での治療継続
妊娠中の歯列矯正には、普段よりもトラブルが起こりやすくなります。ただでさえホルモンバランスの乱れや体調不良に悩まされやすくなっているのに、そこへ歯列矯正による負担が加わると、心身ともに限界を迎えてしまうかもしれません。そんな時に意識していただきたいのは「体調」を優先することです。もちろん、歯列矯正を継続させることも大切なのですが、妊娠・出産を成功させることの方が重要です。体調を崩した上で歯列矯正を成功させても、後悔しか残りません。ですから妊娠中は出産を無事に終えることを第一に考えながら、歯列矯正に取り組むようにしましょう。
【2】妊娠中の歯列矯正で注意すべきこと

妊娠中の歯列矯正では、妊娠性歯肉炎(にんしんせいしにくえん)と歯周病対策に注意しなければなりません。
① 妊娠性歯肉炎
妊娠性歯肉炎とは、文字通り妊娠期に発症する歯肉炎です。一般的な歯肉炎は、歯の表面に歯垢や歯石が堆積し、そこで歯周病菌が繁殖することが主な原因となりますが、妊娠性歯肉炎の場合はそこにホルモンバランスの乱れが加わります。具体的には、歯周病菌のエサとなる女性ホルモンの分泌が増加するため、その活動が活発化して歯茎が腫れやすくなるのです。
ただ、妊娠性歯肉炎はあくまで「歯肉炎」であり、産後にホルモンバランスが正常化されれば、その症状も軽くなっていくため、深刻に悩む必要はありません。とはいえ油断をすると歯肉炎から歯周炎へと移行し、歯茎が下がったり、歯槽骨が溶けたりする症状が見られるようになるため、適切な対策をとる必要があります。ちなみに、妊娠中の歯周炎を重症化させると、早産・低体重児出産のリスクが上昇します。これは妊娠期においてもっとも避けるべきトラブルのひとつなので、妊婦さんはその点も踏まえた上で歯周病対策を講じていきましょう。
② 歯周病対策
妊娠期の歯周病対策も基本は普段と変わりません。毎食後の歯磨きをしっかりと行って、歯周病菌の温床となる歯垢・歯石が堆積しないよう努めましょう。上述した通り、妊娠中は普段よりも歯周病リスクが高くなっていることから、セルフケアだけで対策するのは難しいです。可能であれば妊娠中も歯科医院でのクリーニングや歯石除去を行うスケーリングを受けて、歯周病の予防効果を高めていきましょう。もうすでに歯肉炎を発症している場合は、安定期に歯周病治療を受ける必要があります。母子ともに安定する妊娠中期ならほとんどの歯科治療を受けられます。
【3】妊娠中に避けるべき処置
妊娠中期の歯科治療となると、お腹の赤ちゃんへの悪影響が気になるところです。特に以下の3点については、事前に正しい知識を持っておいた方が良いといえます。
① 麻酔なしでも歯列矯正は進められる?
歯列矯正は、基本的に麻酔なしで治療を進めていくことが可能です。ただし、便宜抜歯や矯正用アンカースクリューを埋入する時に限り、麻酔が必要となります。どちらも歯列矯正の早い段階で行う処置なので、妊娠や出産に影響が出ないタイミングをはかりやすいことから、過剰に心配する必要はないといえます。
② レントゲン撮影はしなくてもよい?
歯列矯正でレントゲン撮影を行うタイミングは、治療を始める前の段階です。一般的には精密検査の時に行うだけなので、妊娠への影響はあまり考えなくても良いといえます。妊娠中にレントゲン撮影が必要となったとしても、安定期なら問題なく行えます。よって、歯周病や虫歯治療でレントゲン撮影が必要になった場合は、妊娠中期に受けることが推奨されます。
③ 歯列矯正中の薬の服用は?
歯列矯正に関連した服薬というのは、おそらく鎮痛剤に限られます。鎮痛剤の中には、妊娠中でも安全に服用できるものがありますので、歯科医師や薬剤師のアドバイスを聞きながら薬剤を選択するようにしてください。その他の薬剤の服用が必要になった場合も必ず専門家の指示を仰ぐようにしましょう。
【4】体調優先で治療を進めましょう

歯列矯正と出産のどちらが重要か。それは言うまでもなく出産です。歯列矯正のせいで体調を崩したり、お腹の赤ちゃんに負担がかかったりするようなことは避けるようにしてください。妊娠中の歯列矯正では、体調を優先して以下の3つのポイントを意識しましょう。
① 体調が優れず定期診察が難しい時
妊娠による影響で体調が悪く、定期的な通院が難しい時は無理せず自宅で安静に過ごしましょう。矯正歯科には事前に電話連絡することで、快く承諾してくれるはずです。ただ、装置の調整などを1ヵ月以上遅らせるのはあまり良くないため、自分の体調と相談しながら、できるだけ早い時期に次の予約を入れるようにしましょう。
② 分娩時の装置の取り扱い
分娩の時は、装置の種類によって取り扱いが変わります。インビザラインのような着脱式の装置を使っている場合は、分娩時に装置を取り外せます。固定式のワイヤー矯正の場合は、基本的に装置を着けたまま出産に臨みます。
③ 出産後の治療再開
出産後は少なくとも1ヵ月、可能であれば3ヵ月程度はお休みするのが望ましいです。出産後の治療再開時期は、主治医としっかり相談した上で決めるようにしましょう。