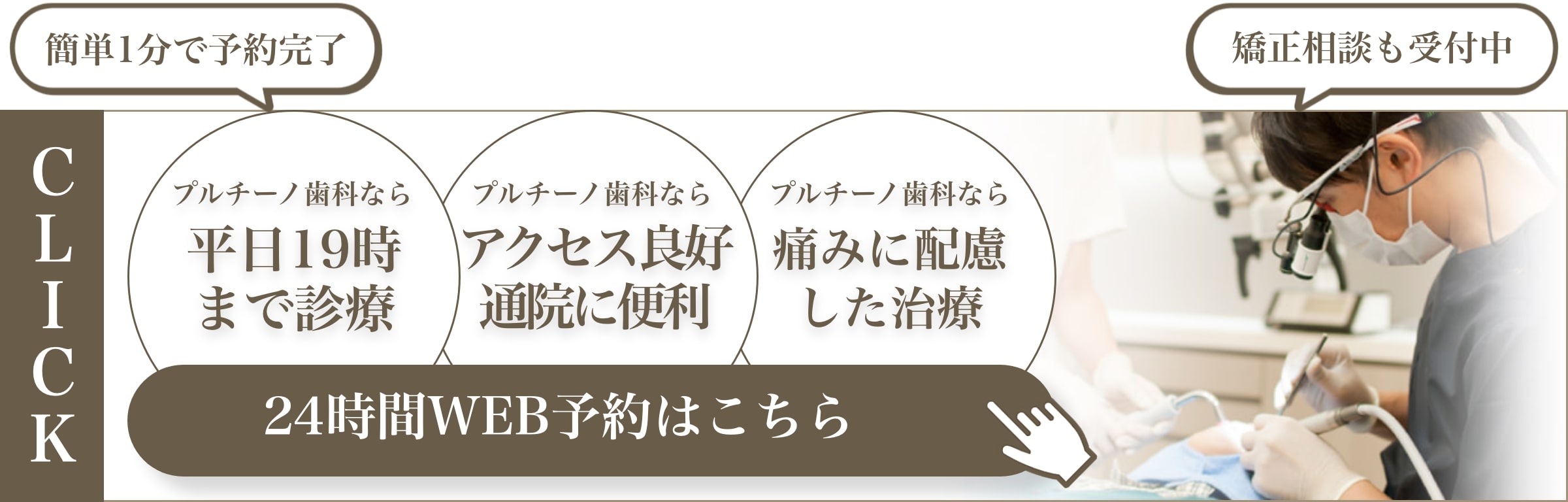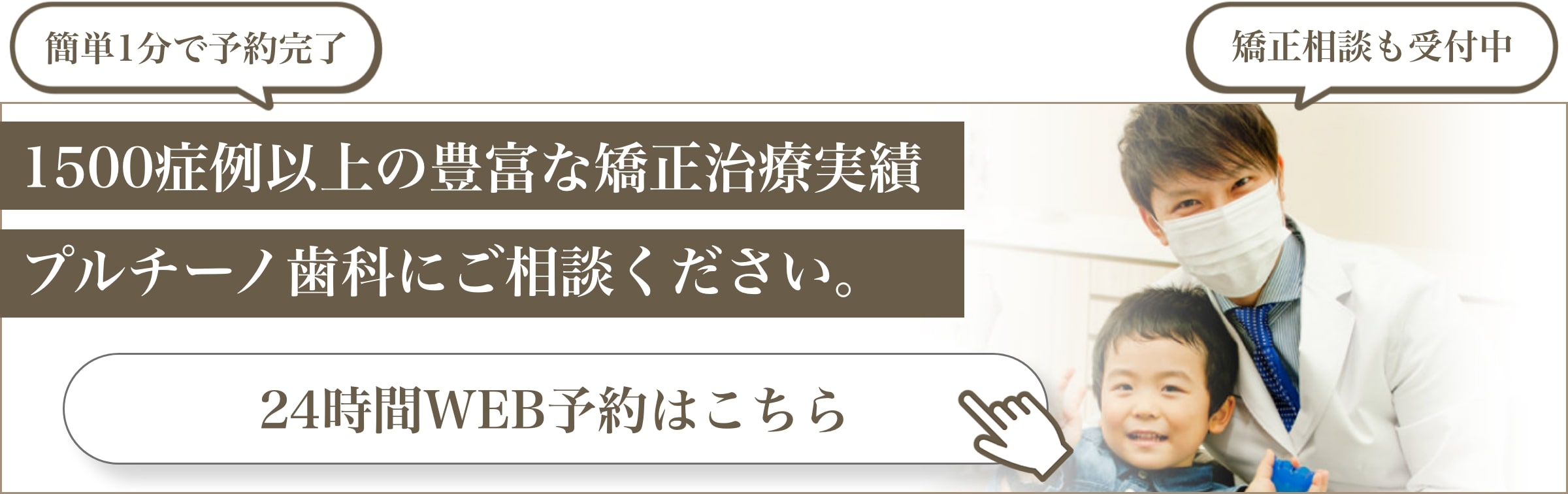矯正歯科治療では、多くのケースで「ゴムかけ」と呼ばれるプロセスが必要です。矯正治療を受けたことがない方にとっては、イメージしにくい処置なので、何の目的で行って、どのような方法で実施するのかもよくわからないと思います。今回、四日市のプルチーノ歯科・矯正歯科が、ワイヤー矯正やマウスピース矯正などの歯列矯正で必要なゴムかけの目的、種類、方法について詳しく解説します。
目次

1.矯正治療での「ゴムかけ」ってなに?
矯正治療におけるゴムかけは、上下の顎にまたがって矯正用のゴムを引っ掛ける処置です。通常は、歯並びの細かい調整が終わり、仕上げの段階に入りつつある時に行います。歯並びや噛み合わせの状態によっては、矯正治療の前半からゴムかけを行う場合もあります。ゴムかけは、ワイヤーや矯正用マウスピースでは得ることが難しい矯正力を発揮するため、歯列矯正においてかなり重要な役割を果たしています。
2.「ゴムかけ」の実施で期待できる効果について
矯正治療でゴムかけを実施すると、以下のような効果が期待できます。
① 細かく歯を動かすことが可能
矯正治療で使うゴムはとても小さく、柔軟性が高いです。そのため歯と歯の間に引っ掛けることで、かなり強い矯正力を働かせることができるのです。ゴムをかける部分を工夫することで、歯を細かく移動することも可能です。この場合は、マルチブラケット矯正装置やマウスピース型矯正装置の補助として、矯正用ゴムを活用します。
② 歯を動かすスペースの確保が可能
矯正用のゴムでは、歯を動かすためのスペースを作ることも可能です。ゴムかけによって歯を任意の場所へと移動できれば、矯正に必要となるスペースを作り出せます。これもメインとなっている矯正装置の補助としてゴムを活用する形となります。
③ 噛み合わせの調整に効果的
ゴムかけによる最も重要な効果は、噛み合わせの調整です。上下の歯列が正常な位置で噛み合うように、ゴムで微調整を加えます。矯正用ゴムは上下の歯列にまたがって矯正力を加えることができるため、上下顎のアンバランスをダイナミックに改善できるのです。これはゴムかけならではの効果といえるのではないでしょうか。ゴムかけを仕上げの段階で行うことが多いと述べましたが、噛み合わせの調整のために行うゴムかけが該当します。
3.「ゴムかけ」の種類と対応している症例
ゴムかけの種類は、大きく4つに分けられます。それぞれ対応している症例についても簡単に説明します。
① 2級ゴム
2級は、矯正歯科の用語で上顎前突を意味します。上の顎が下の顎よりも前に出ているために、出っ歯の症状が現れる歯並びです。そんな上顎前突の症例に対しては、2級ゴムが使われます。2級ゴムを上下の歯列間に引っ掛けて、正常な位置へと誘導します。具体的には、上の歯列を後方に、下の歯列を前方に移動する力を加えます。
② 3級ゴム
3級は、矯正歯科の用語で下顎前突を意味します。下の顎が上の顎よりも前に出ているために、受け口の症状が現れる歯並びです。そんな下顎前突の症例に対しては、3級ゴムが使われます。3級ゴムでは、2級ゴムと逆の力が働きます。
③ 垂直ゴム
垂直ゴムは、開咬(かいこう)の症状を治すのに適したゴムです。文字通り上下の歯列に垂直的な方向でゴムかけをして、不要な隙間を埋めていきます。垂直ゴムはその他にも噛み合わせの細かい調整で用いられることもあります。
④ クロスゴム
クロスゴムは、交叉咬合(クロスバイト)と呼ばれる歯並びに適応されるゴムです。クロスバイトとは、上下の歯の位置関係が反対になり、上の歯が下の歯の内側に入ってしまっている歯並びで、咀嚼障害を起こしやすいです。上下の歯列にまたぐ形でゴムをかけることで、交叉している歯を効率良く正常化できます。
4.「ゴムかけ」の方法
次に、ゴムかけの方法を説明します。
① ゴムかけの装着時間と取り換えるタイミング
矯正用のゴムは、基本的に1日中装着します。食事と歯磨きの時には取り外して、それらが終わったら新しいゴムに取り換えることになります。このルールを厳守しないと、ゴムかけによる適切な効果が得られなくなります。
② ゴムかけを実施する期間
ゴムかけを実施する期間は、症例によって大きく変わります。そもそもゴムかけの種類によって目的も異なり、ゴムかけを始める時期にも違いが見られるのです。その上でゴムかけを実施する平均的な期間は、1年から1年半程度といえます。短いケースでは半年程度でゴムかけが終わることも珍しくありません。
5.「ゴムかけ」で痛みが生じる原因
ゴムかけでは、痛みが生じる場合があります。その原因は以下の3つに分けられます。
① 歯が移動するための圧力
ゴムかけでは、特定の歯や歯列全体に対して、かなり大きな矯正力が働きます。それに伴い歯も大きく移動することから、相応の痛みや不快症状が生じます。これはマルチブラケット装置やマウスピース型矯正装置で歯が動く時の痛みと同じです。
② ゴムが接触することによる刺激
ゴムかけの位置や歯列の状態によっては、ゴムが口腔粘膜と接触して刺激することがあります。これは物理的に避けられない痛みであるケースが多く、しばらくは我慢する他ありません。もちろん、極端に強い痛みが生じている場合は、主治医に相談して調整を加えてもらう必要があります。
③ ゴムの使用方法がそもそも間違っている
ゴムかけのゴムは、基本的に患者さん自身が着脱します。ゴムのつけ方や外し方が間違っていると、歯や歯茎に不要な刺激が加わって痛みが出る場合があります。
6.「ゴムかけ」を怠ったらどうなるのか?
ここまでは、矯正歯科のゴムかけの目的や種類、痛みについて解説してきましたが、ゴムかけを怠った場合にどんな弊害が生じるのかも気になるところです。
① 治療にかかる期間や治療後の仕上がりへの影響
ゴムかけは、歯列矯正を終わらせる上で必須となる処置です。そのゴムかけを怠ってしまったら、いつまで経っても矯正が終わりません。その結果、治療期間が長引いたり、仕上がりが悪くなったりしてしまいます。
② 移動した歯が元の位置に戻っていく
ゴムかけを怠ると、当然ですが歯に適切な矯正力がかからず、元の位置へと戻っていってしまいます。せっかく時間をかけて動かした歯が後戻りしてしまうことは、患者さんにとって何よりも大きなデメリットとなります。
③ 噛み合わせの問題が起こる可能性がある
ゴムかけの主な役割は、上下の歯列の噛み合わせを正常化することです。そのため歯列矯正の後半から終盤にかけてゴムかけを行うケースが多くなっています。そんなゴムかけを歯科医師の指示通りに行わないと、上下の噛み合わせを正常化することができず、大きな問題を抱えたまま歯列矯正を終了せざるを得なくなる場合もあります。噛み合わせはある意味で、歯並び以上に重要なものなので、正常な咀嚼機能を手に入れるためにもゴムかけはきちんと行うようにしましょう。
7.まとめ
今回は、矯正歯科の治療で必要となるゴムかけの目的や種類、方法について、四日市のプルチーノ歯科・矯正歯科が解説しました。矯正のゴムかけは、上下の歯列のアンバランスを大きく改善できる方法で、治療の後半で必要となることが多いです。矯正の前半でも歯と歯の距離を効率良く縮めたり、逆にスペースを作ったりする際にゴムかけを行うこともあります。そんな歯列矯正のゴムかけについてもっと詳しく知りたいという方は、いつでもお気軽に当院までご相談ください。当院では矯正歯科の相談・カウンセリングを無料で承っております。